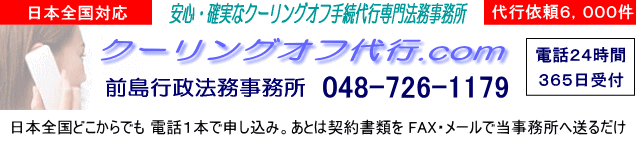| 法律 |
| 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、 |
| ①将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき |
| ②断定的判断を提供し、当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認をした結果、 |
| 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 |
| 法律の解釈 |
| ①「将来における変動が不確実な事項」の例示としては、 |
| ア「将来における契約の目的物の価額」とは、 |
| 例えば不動産取引に関して、将来における当該不動産の価額など |
| イ「将来において当該消費者が受け取るべき金額」とは、 |
| 例えば保険契約に関して、将来において当該消費者が受け取るべき保険金の額など |
| ウ「その他の」将来における変動が不確実な事項とは、 |
| 消費者の財産上の利得に影響するものであって将来を見通すことがそもそも困難であるもの (例えば証券取引に関して、将来における各種の指数・数値、金利、通貨の価格)をいう。 |
| ②「断定的判断」とは、 |
| 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき、利益を生ずることが確実でないのに確実であると誤解させるような決めつけ方をいう。 |
| 「絶対に」「必ず」のようなフレーズを伴うか否かは問わない。 |
| 例)先物取引において、事業者が消費者に対して「この取引をすれば、100万円もうかる」と告知しても、「この取引をすれば、必ず100万円もうかる」と告知しても、同じく断定的判断の提供となります。 |
| 「断定的判断」に該当しないもの |
| 事業者の非断定的な予想ないしは個人的見解を示すものは断定的判断の提供に当たらない。例えば、「この取引をすれば、100万円もうかるかもしれない」と告知すること) |
| さらに、将来の金利など「将来における変動が不確実な事項」につき、一定の仮定を置いて、「将来におけるその価額」、「将来において当該消費者が受け取るべき金額」につき、事業者が試算を行い、それを消費者に示したとしても、将来における変動が不確実な事項」については、試算の前提としての仮定が明示されている限り、「断定的判断の提供」には当たらない。 |
| 具体例 |
| 断定的判断の提供に該当するもの |
| ■「証券会社の担当者に、円高にならないと言われて外債を購入したが円高になった。 |
| ■借金して契約しても10年後に利益が出ると言われて、一時払いの終身保険に加入したが、配当が悪く損害が出る。銀行から約200万円借りた。その返済総額は293万円だが、10年後の満期金が360万円になると勧められた。しかし、予定通りの配当が出なくなり利息の方が高くなった。 |
| ■商品先物取引の勧誘で、「必ず利益が出る、絶対に損はさせない」と説明さて委託契約を結んだ場合。 |
| ■証券会社から、ある株購入の勧誘を受け「短期間で5000円まで値上がりします。」と言われ契約した場合。 |
| ■電話勧誘で「当社の講座を受講すれば必ず試験に合格します。」といわれて契約をした場合。 |
| ■進学塾の説明会に行ったところ「定期試験で絶対80点以上取れると説明をうけて契約した場合。 |
| 断定的判断の提供に該当しないもの |
| ■「当社の住宅は雨漏りしません。」 |
| →住宅の性能は、価格・金額に当たらない。 |
| ■「当校に通えば、TOEIC 800点も夢じゃない |
| →点数は、価格・金額に当たらない。 |
| ■「今まで元本割れしたことはないので、今後も元本割れしないだろう。」と言われたので金融商品を契約したが、元本割れした。 |
| →個人的見解を示すもので断定的判断には該当しない。 |